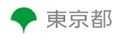「非認知能力」って聞いたことはありますか?「とうきょう すくわくプログラム」*は幼稚園・保育園などで子供たちが好奇心や興味を持って、わくわくしながら遊び、学べるよう応援する取り組みです。この取り組みを通じて「非認知能力」と呼ばれる、子供たちの自己肯定感や思いやりといった、豊かな心の育ちをサポートしていきます。
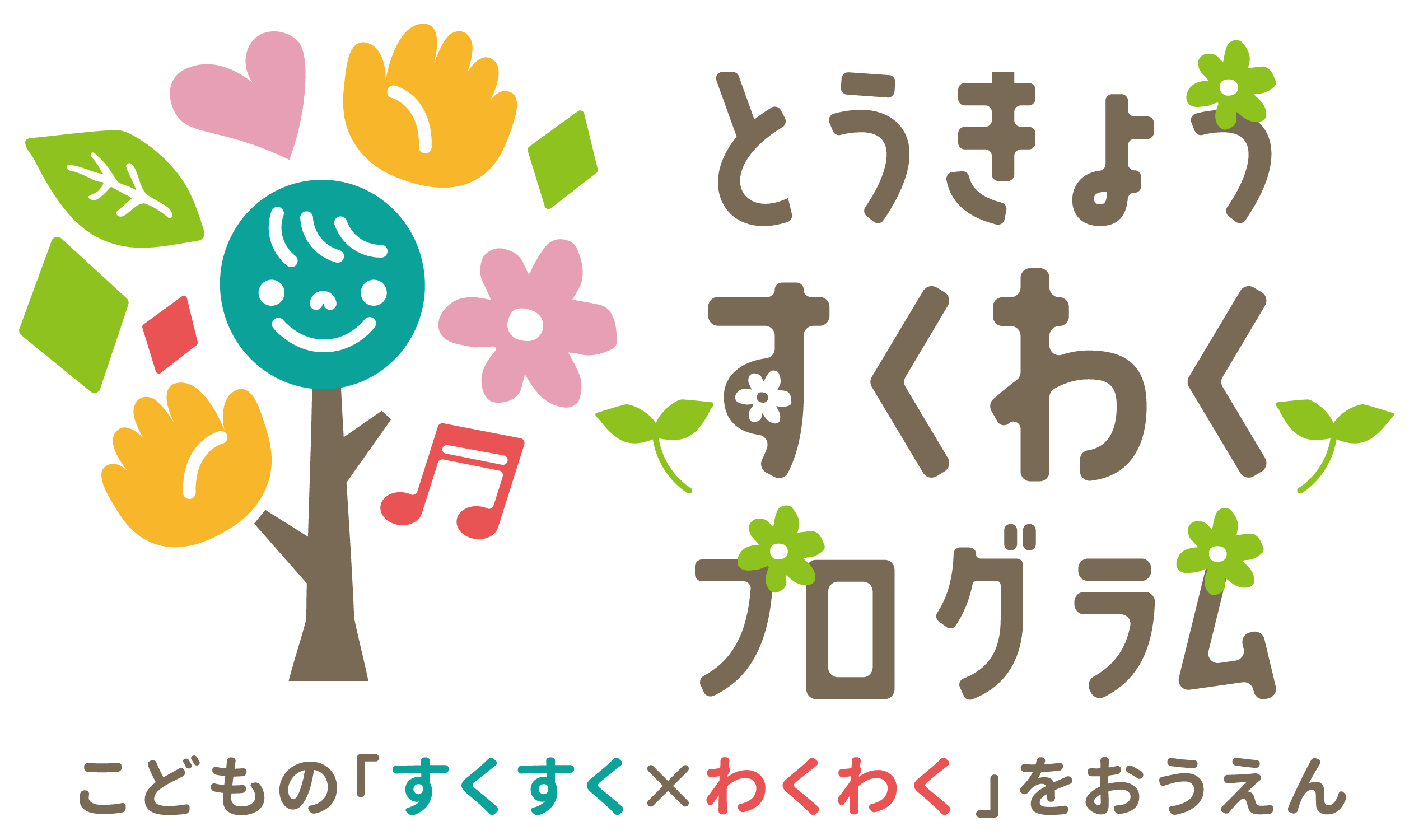
*「とうきょう すくわくプログラム」は
東京都が、東京大学大学院教育学研究科附属
発達保育実践政策学センター(CEDEP)と
連携して取り組んでいます。
「非認知能力」と「とうきょう すくわくプログラム」
についてお話を伺いました!
対談の様子を動画で公開中!
今回は、元バドミントン日本代表、バドミントンペア「オグシオ」の愛称で知られ、二児の母親でもある潮田玲子さんが、東京大学大学院教育学研究科教授であり、CEDEPセンター長の遠藤利彦先生に「非認知能力」と「とうきょう すくわくプログラム」について伺いました。
非認知能力ってなんだろう?
~人の一生涯に渡る心と体の健康や幸せの形成の鍵となるもの~
遠藤先生
「頭の良さ、IQの数値に表れるようなところの力を一般的に認知能力という言葉で呼んでいます。
そこに"非"というのがついているということは、頭の良さ以外の、だけど別の大切な心の力、そういう意味を持っている言葉と考えていただければと思います。
非認知能力は、大きく2種類に分けて考えられ、1つは、"自分自身に関する心の力"、もう1つは"人との関係に関する心の力"、と言っていいかなと思います。"自分自身に関する心の力"というのは、自分のことを大切にして、自分のことを適度にコントロールできて、自分のことをもっともっと良くしよう、高めようとする力。それが自分自身に関する心の力と考えていただければと思います。」
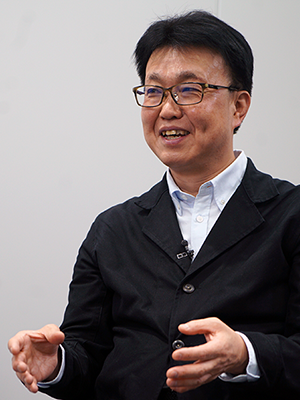
潮田さん 「いわゆる自己肯定感の高い子供といったイメージですか?」
遠藤先生
「そうですね。面白いからやってみたいと好奇心に駆られた意欲であったりとか、やればできるはずという自信であったり、さらには一人で決めてちゃんと一人で実行できるという主体性とか、あるいは自立心と言われているようなものが、心の力の中に含まれていると考えていただけるといいかなと思います。
一方、人との関係に関する力というのは、集団の中に溶け込んで人との関係を作って維持していくための力ですね。平たく言えば、人とうまくやっていくための心の力ということになります。人とうまくやっていくためには、人の気持ちを理解することが必要になるかもしれません。さらには他の人に思いやりを持つ心の性質も重要かもしれないですね。」
潮田さん 「親御さんは優しい子供に育ってほしいというようなことをよくおっしゃるじゃないですか。そういったところで、やっぱりこの非認知能力はすごく大事になってくるっていうことですかね。」
遠藤先生 「自分自身に関する心の力とか、人との関係に関する心の力っていうのは、実は言葉だけではなくて、私たち大人も含めて、人間が日常生活を健全に送るために、おそらくは誰もが直感的にこういう心の力って大切だよね、必要だよねと感じているもの、そう言っていいものなんじゃないかなという気がします。そういうものを幼少期の段階でしっかり身につけていくことが大切だと、今、声高に言われるようになってきています。」
潮田さん 「そうですよね。その幼少期に人格形成じゃないですけど、しっかりと基礎基盤になるようなものを作っていくというのが大事になってくるんですね。」
遠藤先生 「人生の土台づくりだったりするんですが、その土台の部分に関わる非認知と呼ばれる心の力。それをちゃんと身に付けておくことが、実は人の一生涯に渡る心と体の健康、あるいは幸せの形成に対してとても大きい影響力を持っているということが、現在、世界のたくさんの研究の中から示されています。」
潮田さん 「なぜ今、改めて非認知能力の大切さや重要性が注目されているのですか?」
遠藤先生
「実は非認知と呼ばれる心の力っていうのは、言葉で教えて、あるいは知識として与えて身につけさせるというのが意外に難しいものだと思います。実際に子供たちが色々な経験を積む中で培われるものが『非認知能力』、とりわけ色々な人との関係というものが、子供の発達にはすごく重要なわけです。
大人との関係を一般的に"タテの関係" 、同年齢の子供たち同士の関係を "ヨコの関係"、ちょっと年齢が上や下の子供との関係を "ナナメの関係"と言ったりします。本来子供というのは色々な"タテの関係"、色々な"ヨコの関係" 、色々な"ナナメの関係"、その3種類の関係というのを濃密に経験する中で、色々な心の力、とりわけ非認知と呼ばれる心の力を効果的に身につけることができると言われています。
保育園や幼稚園での生活というのが、まさにそういう色々な関係を経験するのに一番子供たちにとって適切な場所になっているかと思います。園での経験というものを充実させていくことが、今回の『とうきょう すくわくプログラム』の1つの狙いになっていると考えていただければと思います。 」
「とうきょう すくわくプログラム」ってどのようなことをしているの?
遠藤先生
「それぞれの園が、子供たちがこういうものに夢中だ、あるいは先生方自身が、こういうものが子供たちにとって、今大切なんじゃないかと色々なことを考える中で、プログラムは生まれていきます。それぞれの園で自由に創造的にテーマを設定して、そのテーマに従って、色々な素材を準備していきます。
例えば、"光"であれば、 太陽の光をイメージするかもしれないし、それは色々な電灯からの光かもしれません。さらには"光"っていうのは、何かを通すと違った色に見えたりする。あるいは、水に反射したりするってこともあるかもしれないし、あるいは、光には影があったりですね。
言ってみれば、子供たちがそういうものを自分で発見していく、何か面白いものないかなって探し回って、自分の好奇心をどんどん広げていくわけです。さらには、これ面白いなって、今度は子供が気付くと、今度は1つのものを選んでどんどん深めていく、"深めていく好奇心"にもなります。"広げていく好奇心"と"深めていく好奇心"の両方がちゃんと体験できるように工夫がされているプログラムと考えていただけるといいかと思います。」

潮田さん
「私は元アスリートということもあって、やっぱりスポーツの中でそういった人間力みたいなものを育んでほしいなって子供たちに思うことがたくさんあるんですけど、そういった仲間と協調性を持ったりだとか助け合ったりだとか、それをこのプログラムで園に通いながら学べるってすごくいいなと素直に感じました。
私自身もそうなんですけど、子育ての中で、例えばうちの子はまだオムツが取れていないと心配したりだとか、小学校に上がる前までにひらがなって書けるようになってた方がいいんじゃないかなとか、そういう心配をしていると思います。でも準備にフォーカスするのではなくて、その時期にしっかりと遊びの中で探究し、色々なことを求める方がすごく大切だと伺って、本当に響く保護者の方々って多いんじゃないかなっていうのは素直に思いました。」
実際にどのようなプログラムを行っているか気になる方はこちら!
「とうきょう すくわくプログラム」
広がっています!

「とうきょう すくわくプログラム」の探究活動についてもっと知りたい方はこちら!
学習院大学文学部教授・東京大学名誉教授・
東京都 こども未来会議委員の秋田喜代美先生に、
解説していただきました。